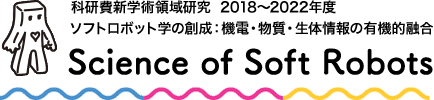イベント
ロボティクス・メカトロニクス講演会2025シンポジウム『 “いいかげん”を科学して未来を創るソフトロボット学6』
- 日時
- 2025年6月4日(水)13時~17時
- 場所
- やまぎん県民ホール(スタジオ1)&オンライン(Youtubeライブ配信予定)
***下記より、事前参加登録をお願いいたします!(参加費無料)***
事前参加登録フォーム
概要:
やわらかい電子回路や機械、やわらかい材料、やわらかな情報処理など、“やわらかさ”に関連した色々な研究をうまく結び付けて、新しいロボットを目指していく「ソフトロボット学」(通称:ソフロボ)が、世界中で活発に研究されている状況が続いています。この学問の最大のポイントは、異なる分野の専門家が集まり、協働する“異分野融合”によって、これまでのロボットにはなかった融通・適応・好い加減さ、といった新しい価値を作り出していくことです。6回目となる今回のシンポジウムのテーマは、“Beyond Control”です。すなわち、ソフトロボットをうまく機能させるための“制御を越えた何か”を議論します。関連する研究者の講演をベースに議論を深めるとともに、ソフトロボット学のめざす“いいかげんさ”の科学を、やわらかく解説することを目指します。また、若手~中堅ソフロボ研究者にも、未来のやわらかいロボットを大いに語ってもらいます。ロボットの専門家でない方の参加も大歓迎です。
参加費:無料
参加方法: 現地参加 / Youtubeライブ配信(予定)
プログラム:
(※変更の可能性があります)
13:00~13:40 【趣旨説明&ソフロボ研究者からのメッセージ1】
「ソフトロボットの制御: 絶望からの一手をやわらかく考える」
望山 洋(筑波大学)

ソフトロボットは,超多自由度、超劣駆動、超劣観測、環境の超不確かさ、タスク記述の超困難を伴うシステムであり,従来のシステム制御の立場では,どう考えてもうまく制御する望みは薄い.一方,動物は,やわらかい身体をもちながら,なぜ巧みで美しい運動を実現できるのか?いま,従来のシステム制御の固定観念から脱却して,新しいものの見方が必要とされている.本講演では,絶望の淵から,新たな一手に繋がる可能性となる断片を集め,議論の糧となることを目論見る.
筑波大学システム情報系教授.2024年8月より,マレーシア校(学際サイエンス・専門学群)の担当となり,年の4分の3を常夏の地Kuala Lumpurで働く.ソフトロボットのシステム制御に強い関心を持つ.「ソフトロボット学入門: 基本構成と柔軟物体の数理」(オーム社, 2023)および“The Science of Soft Robots: Design, Materials and Information Processing” (Springer, 2023)では,主にロッド理論の解説を担当.博士(情報科学).
13:40~14:00 【ソフロボ研究者からのメッセージ2】
「ソフトロボティクスの冒険」
新山 龍馬(明治大学)

ソフトロボティクスがこれからどこへ向かうのかは、私たち研究者がどれだけ勇敢かつ大胆なビジョンを持てるかにかかっている。国際的な研究動向を踏まえつつ、あるいは無視しながら、さまざまな角度からやわらかいロボットのポテンシャルを考察する。
ロボット研究者。明治大学理工学部機械情報工学科 専任准教授。2010年に東京大学大学院 学際情報学府博士課程修了、博士号取得。2010年から2014年まで、マサチューセッツ工科大学で研究員。2014年より東京大学大学院 知能機械情報学専攻 講師。2022年より現職。生物規範ロボットおよびソフトロボティクスの研究を主軸として、近年はインフレータブルロボットの研究を精力的に進める。著書に『やわらかいロボット』(金子書房)がある。
14:00~14:20 【ソフロボ研究者からのメッセージ3】
「自励振動で目指すフィジカルインテリジェンス」
難波江 裕之(東京科学大学)
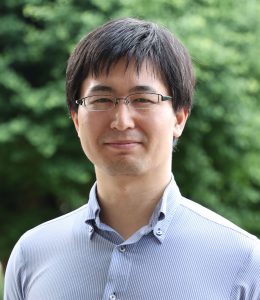
自励振動は,非振動的な入力から振動的な出力を生じる興味深い現象であり,自律性を有するものであると感じている.
自励振動を用いたアクチュエーション技術を基に,知的な動作をフィジカルなシステムによって実現しようとする講演者の取り組みを紹介する.
東京科学大学工学院准教授.2015年東京大学大学院工学系研究科博士後期課程修了,博士(工学).2015年より東京工業大学(現東京科学大学)助教.2025年より現職.
14:20~14:45 【ソフロボ研究者からのメッセージ4】
「「いいかげんさ」を活用する生命のシステム」
鈴森 康一(東京科学大学)
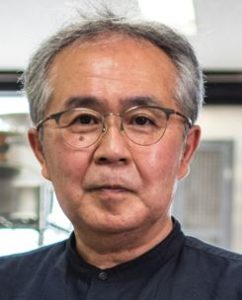
農業革命と産業革命を経て,科学技術の役割は「パワーと精度」から「持続と多様」
にうつり変わっている.生きものは「持続と多様」実現のために,「いいかげんさ」
を活用している.厳密なコントロールはかえって妨げになる場合がある.いくつかの
例をもとに,ソフトロボット研究を通じて近ごろ感じることを語らせて頂きたい.
1984-2001年 株式会社 東芝 勤務
1990年 横浜国立大学大学院博士課程修了
2001-2014年 岡山大学教授
2014-2025年 東京工業大学および東京科学大学教授
2025年~ 東京科学大学名誉教授および福島国際研究教育機構パワーソフトロボ
テイクスユニットリーダー
(15分休憩)
15:00~15:30 【ソフロボ未来を語る講演1】
「身体がもたらす自律的な知性」
吉田 尚人(京都大学)

動物はさまざまな行動を行うことができる。歩く、走る、物に近づく、食べる、物を作るなど、多種多様な行動は、生き延びるために統合されている。人工物、すなわちロボットとして動物を捉えたときに驚くべき点は、これら多様な行動やその獲得に関わる学習メカニズムが、脳内で完結しており、外的な装置に依存しない完全に自律的な学習機械として機能している点である。本講演では「身体を持つ自律的学習ロボット」という視点から、伝熱・電気化学的ダイナミクスといった外からは見えにくい内的特性に注目し、その意味を探る。この観点から、ロボットの内的状態変化とその安定化(=恒常性)だけを目的とした、計算論的神経科学に着想を得た行動最適化の仕組みを導入することで、一見すると我々にとって“無目的”に学習しているかのように見えるAIが、環境とのカップリングを通じて多様な行動を生み出せること、そしてそれが実際の動物の行動をうまく説明できるという最近の成果について紹介する。
京都大学 特定研究員、博士(情報理工学)。スタートアップ企業での家庭用ペットロボット研究開発の後、東京大学大学院 情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻で博士号を取得。計算論的神経科学と生理学の原理に基づくロボット行動生成の研究に興味を持つ。現在は学術変革領域A「クオリア構造学」クオリア構造の記号創発システム論で記号創発の研究に従事。自律型AIの貢献に対しWBAI奨励賞を受賞。
15:30~16:15 【ソフロボ未来を語る講演2】
「Embodied Intelligence: A New Paradigm for System & Control(身体性知能とシステム・制御)」
大脇 大(東北大学)
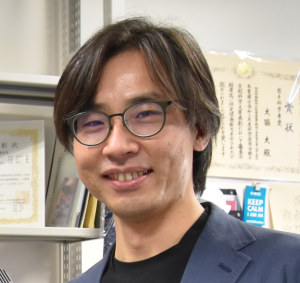
知能とはなにか?この問に対し,「知能的な振る舞いを生み出すシステムには,主体の物理的実体と環境との相互作用,すなわち,身体性(Embodiment)が不可欠である」とする概念が提唱されてから30 年あまりが過ぎた.ビッグデータや機械学習の実用化などの技術革新を基盤とした第3次AIブーム,われわれの生活様式を一変させた世界的パンデミックなど,時代が大きく変化しつつある昨今,予測不能的に絶え間なく変わり続ける実世界の複雑性に対応し,柔軟かつ適応的に振る舞う知能システムが未来の社会を支える科学技術の鍵となる.そのため,実世界との関わりから生じる知能やシステム・制御論の重要性は益々高まっている.身体性知能(Embodied Intelligence)に基づくシステム・制御のアプローチは,従来の工学的なアプローチにみられるような,システム全てを厳密にモデル化し統御するアプローチとはコンセプトが大きく異なる.本講演では,3名の講演者それぞれが考える身体性知能とシステム・制御のあり方を,最新の研究成果を交えながら議論したい.
東北大学工学研究科ロボティクス専攻准教授.博士(工学).Embodied intelligence,Neuro-rehabilitation, Bio-hybrid systemに関する研究に従事.令和2年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞などを受賞.
福原 洸(東北大学)

東北大学電気通信研究所助教。博士(工学)。2018年3月、東北大学大学院工学研究科電気エネルギーシステム専攻博士後期課程を終了し、電気通信研究所学術研究員を経て、2018年10月より現職。専門は、自律分散システム、生物規範ロボット。動物が示す即時適応的な振る舞いの背後にある制御メカニズムや形態機能の理解に取り組んでいる。
増田 容一(大阪大学)
2019年大阪大学大学院工学研究科博士後期課程を修了。現在、同附属フューチャーイノベーションセンター助教。同機械工学専攻の助教を兼任。

(15分休憩)
16:30~17:00 講演者によるパネルディスカッション+Q&A
コーディネータ:望山 洋(筑波大学)

参加申込:事前参加登録をお願いいたします!(参加費無料)
事前参加登録フォーム
主催:日本ロボット学会ソフトロボティクス研究専門委員会
科研費新学術領域研究「ソフトロボット学」
ROBOMECH2025主催:日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門